監修者からのメッセージ
私は博士課程終了後、東芝研究所に入社し、電機メーカーが何社も参加している大型国家プロジェクトで、半導体の生産装置、半導体のあるプロセスの過程をつくる研究開発を行なっていました。
半導体は常に「最先端」でなければなりません。
そのため、多額な資金が必要な科学的研究に用いられるような装置が製造技術として使われていました。そして同時に量産もしないといけないのですが、その時「半導体の研究っていうのは、研究だけをしていてもダメだ」ということを理解したのです。
東芝では実際の生産設備の中で研究していたのに対し、他社は実験用の設備で研究しており、その中で研究・実験がうまくいったとしても実際の生産設備に組み込んだらうまくいかない・・・というケースが多かったからです。
装置を使用するのは生産現場です。
だからこそ最初から生産を想定して考えた「生産優先」の仕組みが必要です。
半導体の世界では、世界最高性能が出すのが当たり前で、それらが商品となって売れなくては意味がありません。
どんなにすごい性能を出しても、安定的な性能を出すためには生産技術を理解していないと、歩留まり(生産数における良品の割合)が出ません。
これはDXにもいえることで、どんなに優れたシステムや装置を導入してDXしようとしても生産現場に適していなければ無駄になります。
それぞれお客様によって生産現場は全く異なるため、その生産現場に応じたDXの進め方があるのです。
製造業DXを実現するためには、まず最初に「原材料の入荷から製品の出荷まで、生産工程をタートルチャートで整理すること」から始めます。
そして生産工程の仕組み一つ一つをモデルとして論理的に数値化してデータを積み重ねていきます。
すると、どんなに複雑なものでも「これがあったからこうなった」という関連性──すなわち因果関係が見えてきます。
どんなに複雑なものでも必ず原因があります。この「原因究明」が実は大変なのですが、数値があれば、さまざまな関係性のあるパラメーター(変数)を見比べることで、統計的に見えてくるのです。
例えば、生産現場でありがちな「最高性能のものを作ろうとすると歩留まりが数10%、ここまで妥協すれば100%」という話ですが、できることなら「最高性能のものを100%作りたい」と皆さん思っているはずです。
それを100%に近づけるために必要なものが「数値」なのです。
数値化されたデータに基づいて判断やアクションを起こす──これがデータドリブンです。
製造業は特に明確な数値が出ますから、そういった点でも改善しやすいと言えます。
デジタル技術で数値化することで目標設定が可能になる。その数値をもとに原因を探ってより改善していく──この一連すべてが「製造業DX」なのです。
生産現場でバリバリ働いている人ほど全体感ではなく一部分だけに目を向けてデジタル化しようとしがちです。
それでは部分的にしかDXは進みません。
だからこそ「一度立ち止まって全体を見渡す」そして「あ、こんな手があったんだ」という気づきを体感することが大切です。
DXは一過性ではなく習慣化させなくてはいけないのです。
そのためには、社内にリードしてくれる人。アントレプレナーシップ(起業家精神)をもった推進者が必要です。
「プランして、仮説を立てて、仮説を検証する」というサイクルを高速回転しなくてはいけないので、マネジメントの基礎が理解できる人が必要です。
FRICS Fabの「製造業DXの内製化を実現する人材開発・リスキリング講座」は、そういった「マインド」と「スキル」の両方を学ぶことが可能です。
これからDXしようという製造業の方はもちろん、すでにデジタル化している方にも、改めてリスキリングしていただき、DXを内製化で自社の課題を改善していただければ嬉しいです。
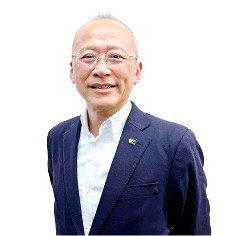
〈プロフィール〉
1984年 広島大学大学院工学研究科材料工学専攻・博士課程終了後、東芝総合研究所 VLSI 研究所を経て、1991年~2001年Burr Brown(アリゾナ,ツーソン)及び2001年~2010年 Texas Instruments(テキサス,ダラス)の オーディオ・イメージング事業部において、デザイン・マネージャー、テクノロジーセンター長を歴任。2004年にはTIフェローに就任。
2010年~2024年 鶴学園 広島工業大学情報学部教授、IoT技術研究センター長(2018年設置)として グローバルな視点から「ものづくり」を担うエンジニアの教育と指導に取り組む。
2024年~ 株式会社TD Holdigns DX推進部 上級顧問に就任。